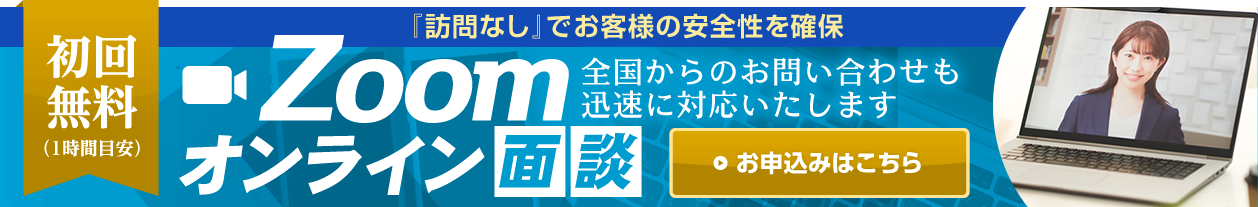相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
名義預金と相続税
2025.10.10
相続税の税務調査で申告漏れとして指摘されるもののトップが「名義預金」です。
実際にこの「名義預金」があった場合、皆さまはどのように取り扱うでしょうか。
今回は、この名義預金があった場合の相続税の計算や申告について解説したいと思います。
相続税がかかる財産
相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金や特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
そして、注意しなければならない点は、財産の名義にかかわらず被相続人に帰属する財産は相続税の課税対象となるため、仮に家族などの名義の預貯金や有価証券であったとしても、真の保有者が被相続人であるものは、相続財産として相続税の申告が必要になります。
相続税の申告の実務でも、家族名義の預貯金(名義預金)や家族名義の株式(名義株)は申告漏れとなることが多く、申告書提出後の税務調査でも申告漏れとして指摘されることが最も多い財産となっています。
名義預金とは
相続税申告の実務における「名義預金」とは、「被相続人が家族等の自分以外の名義で作った預金」をいいます。法律上の定義はなく、あくまでも実態で判断されます。
例えば、父親が子供の名義で口座を開設して父親のお金を預けているケースや、夫のお金であるけれども日常の使い勝手を良くするために妻名義の口座にしているケースなどが名義預金とみなされます。
ここで、どのようなものが名義預金となるか、その判断基準を整理してみましょう。
(1)資金の拠出者はだれか
名義預金か否かの判断の際に、誰がその資金を出しているかはとても重要なポイントです。
例えば、夫が妻に手渡した生活費の一部を、妻が自分名義の預金として蓄積していたようなケースです。妻名義の預金なので相続財産にはならないと思われがちですが、資金の拠出者が夫であり、妻への贈与の事実がない場合には、名義預金(夫の財産)と判断されます。
夫婦の間では名義預金とみなされるケースがよくあるので注意が必要です。
(2)名義人が口座の存在を認識しているか
次に、口座の名義人が、その口座の存在を知っているかどうかも重要なポイントです。
例えば、子や孫の名義で口座を作り、親や祖父母が資金を出してその口座に預けているケースの場合、子や孫の将来のためにと純粋な思いで預金したものであっても、口座の名義人である子や孫本人がその口座の存在を知らない場合は名義預金に該当します。
(3)口座の管理者はだれか
預金口座をだれが管理・支配しているかも重要なポイントになります。
口座を管理しているのが口座の名義人ではなくお金を出した人の場合には、名義預金と判断される可能性が極めて高くなります。
よくあるケースとして、親や祖父母が子や孫名義の口座にお金を移している場合において、子や孫に無駄遣いさせないよう、通帳や印鑑、キャッシュカードなどを親や祖父母が管理しているような場合です。
子や孫が幼い場合には親権者の立場として容認されることもありますが、成人した後も親や祖父母が管理しているケースでは、名義が子や孫であっても、口座の真の保有者は親や祖父母と判断され、名義預金とみなされる可能性が高くなります。
相続財産になる否かの判定
名義預金として相続財産に該当するかどうかの判定は、上記のような様々な角度から実態を確認し判断することが必要になります。
単に名義だけで判断するのではなく、資金の拠出者や口座の形成過程、その後の管理支配の状況等を総合勘案して、口座の真の保有者はだれかを判断しなければなりません。
もし、遺産の中に名義預金と疑われそうな口座がある場合には、上記の判断基準を参考にご検討いただき、申告漏れと指摘されないようご留意ください。
今後の参考になれば幸いです。
東京・銀座で相続・贈与でお困りの方は、お気軽にご相談ください
東京・銀座の相続専門の税理士法人レガートでは、相続税のプロである税理士が、節税を意識しながら、相続税に関わる問題解決に向けて、しっかりとご支援いたしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
また、レガートのコンセプトは、『税務調査が来ない申告』です。
税務調査が圧倒的に少ない点が当法人の申告の特徴であり、多くのお客様にその価値を実感いただいております。
詳しくは下記のページをご覧ください。
レガートが目指す税務調査が来ない申告
税理士法人レガート 税理士 服部誠
相続専門の税理士法人レガートは、東京都中央区銀座より、相続・贈与にまつわるさまざまな情報発信をしております!
相続・贈与に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
詳しくは「相続専門サイト」をご覧ください。
- 初回無料面談のお申し込み
- お電話でのお問い合わせ
0120-955-769 - お電話でのお問い合わせ